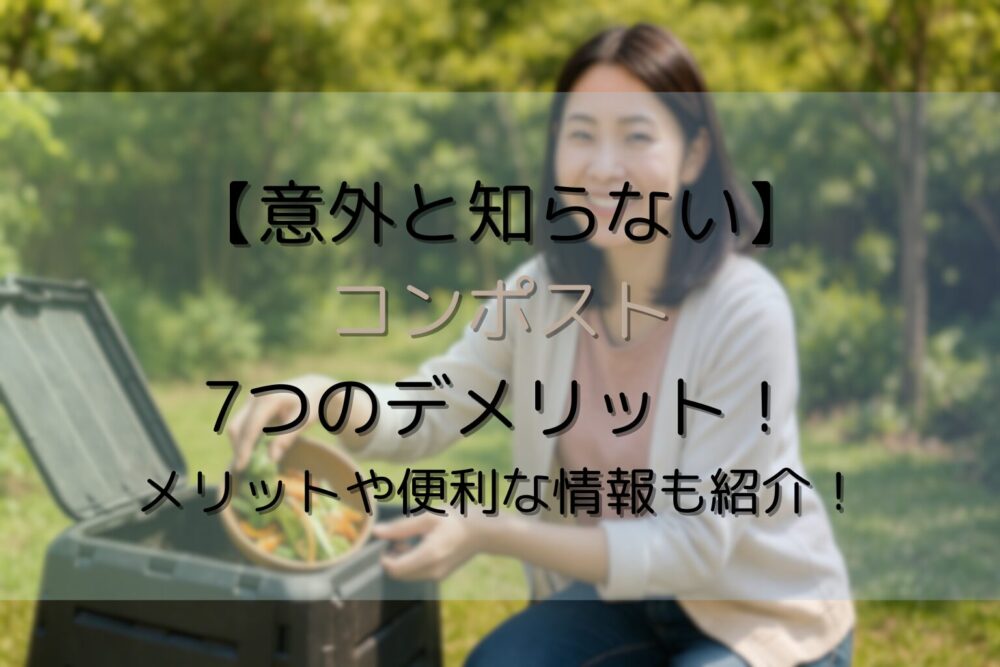コンポストのデメリットとして臭いが気になったり、分解に時間がかかると言われています。
そのため、においに敏感な人や、即効性を重視する人にはおすすめできません。
一方、メリットとして生ごみの削減でごみ袋代の節約になったり、自宅で簡単に堆肥が作れるため、一度「使ってみたい」「試してみたい」という人も多いでしょう。
そこで今回は、コンポストのデメリットを中心に調査。
メリットとデメリットを知り、正しく使用していただくための情報をお届けいたします!
- コンポストのデメリット
- コンポストのメリット
- コンポストをおすすめする人の特徴
- コンポストをおすすめしない人の特徴
- コンポストを始めたい人や初心者のための便利な情報や注意点など
- コンポストのおすすめ商品
コンポストの7つのデメリットと解決策!

早速、コンポストについて、デメリットと解決策を紹介します。
- コンポストの臭いが気になることがある
- 害虫が発生するリスクがある
- 設置場所の確保が必要
- 分解に時間がかかる
- 管理に手間がかかる
- 対応できない生ごみがある
- 冬場は分解が遅くなる
臭いが気になることがある
コンポストは生ごみを分解する過程で、特有の発酵臭や腐敗臭が出ることがあります。
特に通気性の悪い場所や、湿度・温度のバランスが崩れると、臭いが強くなることも。
マンションのベランダや住宅が密集した地域では、近隣への配慮も必要になるケースがあります。
上手に管理すれば臭いを抑えることもできますが、初心者にとっては少しハードルが高いかもしれません。
解決策はある?
臭いを防ぐためには、まず生ごみの種類や水分量に気をつけることが大切です。
水分の多いごみは臭いやすいため、新聞紙などで軽く水気を取ってから投入すると効果的です。
また、こまめにかき混ぜて空気を入れることで発酵が進み、悪臭の原因となる嫌気性分解を防ぐことができます。
専用の消臭材やおがくずを混ぜるのもおすすめです。
慣れてくると、自分なりの臭い対策も自然と身につくでしょう。
以上からコンポストは、
- 臭いが出る可能性がある。
- 管理次第で臭いを抑えられる。
ということを覚えておきましょう。
 ハクブン
ハクブンちゃんとお手入れすれば、ほとんど気にならなくなるって聞いて安心したわ〜!
 シナモン
シナモン発酵臭の管理には、素材のバランスと通気性の確保が大切です。定期的な撹拌も有効です。
害虫が発生するリスクがある
コンポストには生ごみを投入するため、コバエやハエなどの害虫が寄ってくることがあります。
特に気温が高くなる季節は発生しやすく、卵を産みつけられることもあるので注意が必要です。
また、密閉性の低い容器や、食品の処理が不十分な状態で使うと、そのリスクが高まります。
虫が苦手な方には、精神的な負担になる可能性もあるかもしれません。
解決策はある?
まず、ごみを投入する前にしっかり水気を切ることが重要です。
次に、害虫が好む生ごみ(特に果物の皮など)を土やおがくずでしっかり覆うようにすると、匂いや見た目を抑えられます。
また、通気口にネットをかけたり、蓋付き容器を使うことで物理的に侵入を防ぐことが可能です。
少しの工夫で、害虫の発生をかなり軽減できるようになりますよ。
以上からコンポストは、
- 害虫が発生するリスクがある。
- 管理方法次第で防げる。
ということを覚えておきましょう。
 ハクブン
ハクブン虫が苦手だから心配だったけど、ちゃんと対策すれば大丈夫そうね!
 シナモン
シナモンコンポストの衛生管理は防虫対策の基本です。ごみの投入方法にも工夫が求められます。
設置場所の確保が必要
コンポストはある程度の大きさがあるため、庭やベランダなど設置できるスペースが必要です。
狭い住宅や集合住宅では、適した場所が見つからないこともあるかもしれません。
また、日当たりや風通しが良い場所の方が分解が進みやすいので、環境にも気を配る必要があります。
無理に設置すると生活導線を妨げたり、近隣への迷惑になる可能性もあるので、事前の計画が大切です。
解決策はある?
近年は、狭いスペースでも使いやすいコンパクトなコンポストも多く販売されています。
室内に置ける密閉型や、ベランダ用のスリムタイプもあり、設置場所の選択肢が広がっています。
加えて、折りたたみ式や移動可能なタイプもあるため、必要に応じて場所を変えることもできます。
住環境に合ったものを選べば、スペースの制限はそれほど気にならなくなりますよ。
以上からコンポストは、
- 設置場所に配慮が必要である。
- 小型タイプで対応できる。
ということを覚えておきましょう。
 ハクブン
ハクブン省スペースなものもあるなら、マンションでも使えそうでちょっと安心!
 シナモン
シナモン設置環境に合わせて機種を選定することで、効率的な運用が可能になります。
分解に時間がかかる
コンポストの仕組みは、微生物や空気の働きで生ごみを自然に分解させることです。
そのため、分解にはある程度の時間がかかり、すぐに堆肥として使えるわけではありません。
季節やごみの種類によってもスピードが変わり、数週間から数ヶ月かかることもあります。
結果がすぐに見えないことに、やきもきしてしまう方もいるかもしれませんね。
解決策はある?
堆肥化を早めたい場合は、分解を助ける資材や促進剤を使うのがおすすめです。
市販のコンポスト活性剤を加えたり、細かく刻んだごみを使うことで、分解の効率が上がります。
また、適度な湿度と温度を保つことも重要です。
特に夏場は発酵が進みやすいため、積極的に活用することでスピードアップが期待できます。
ちょっとした工夫で成果が早く見えると、続けるモチベーションにもつながります。
以上からコンポストは、
- 時間がかかる性質である。
- 促進剤などで時短が可能。
ということを覚えておきましょう。
 ハクブン
ハクブン急いでる時は分解剤を使うのがいいのね♪早く堆肥ができるのってうれしい!
 シナモン
シナモン発酵促進には微生物の活性化が重要です。定期的な温度と湿度の管理を推奨します。
管理に手間がかかる
コンポストは放置しておけば勝手に堆肥になる、というわけではありません。
適切に分解を進めるには、投入物のバランス、かき混ぜ、湿度や温度の調整などの手入れが欠かせません。
ごみの内容によっては、撹拌の頻度を増やしたり、臭いや虫対策も行う必要があります。
日々のルーティンに組み込む必要があるため、慣れるまでは負担に感じる方もいるかもしれません。
解決策はある?
最近は、初心者でも扱いやすいように工夫されたコンポストが多く登場しています。
自動で攪拌してくれる電動タイプや、水分調整が不要な乾燥式タイプなどを選ぶことで、手間がぐっと減ります。
手動型でも「週1回混ぜればOK」など、管理が簡単な製品もあります。
ご自身のライフスタイルに合ったものを選ぶことで、日々の管理のストレスも最小限に抑えることができそうです。
以上からコンポストは、
- 管理に手間がかかる性質である。
- 便利な製品で負担を減らせる。
ということを覚えておきましょう。
 ハクブン
ハクブン毎日混ぜるのかな?って思ってたけど、自動ならラクに続けられそう♪
 シナモン
シナモン手間を感じる場合は、製品選定の段階で自動化機能付きモデルを検討すると良いでしょう。
対応できない生ごみがある
コンポストには入れてはいけない生ごみがいくつかあります。
たとえば、肉や魚の骨、油分の多い食材、柑橘類の皮などは分解に時間がかかる上、悪臭や害虫の原因になることがあります。
また、プラスチックやアルミ箔などの非生分解性素材も当然NGです。
すべての家庭ごみがそのまま堆肥化できるわけではないため、仕分けの手間がかかる点に注意が必要です。
解決策はある?
事前に「OKな生ごみ」「NGな生ごみ」をリスト化しておくと、毎日の作業がスムーズになります。
市販のコンポストには説明書が付いていることも多いので、そちらを参考にすると良いでしょう。
ごみの分別に慣れてくると、迷うことも少なくなります。
また、一部の高機能モデルでは動物性のものにも対応しているものもあるので、用途に合わせて選べば使い方の幅も広がります。
以上からコンポストは、
- 分別が必要で注意が必要。
- ルール化すれば対応できる。
ということを覚えておきましょう。
 ハクブン
ハクブン入れちゃダメなものって案外多いのね。
ちゃんと表にしておこうっと♪
 シナモン
シナモン投入物の制限を理解しておくことは、安全で衛生的なコンポスト運用の基本です。
冬場は分解が遅くなる
冬の寒い時期になると、コンポスト内の温度も下がり、分解を担う微生物の活動が鈍くなります。
そのため、生ごみの分解スピードが落ち、いつまでも堆肥にならずに残ってしまうことがあります。
また、場合によっては発酵臭がきつくなったり、内容物がカチカチに固まってしまうこともあります。
気温が低い地域では、冬季の運用を工夫する必要があります。
解決策はある?
冬場でも分解を進めたい場合は、コンポストを日当たりの良い場所に設置したり、保温材で覆って内部の温度を保つことが有効です。
また、発酵を促すために米ぬかやおがくずを加えるのもおすすめです。
電動タイプの中には内部ヒーター付きのものもあるため、寒冷地ではそういった製品を選ぶと安定して堆肥化を継続できます。
少しの工夫で冬場も安心して使えますよ。
以上からコンポストは、
- 冬は分解が遅くなる傾向がある。
- 寒さ対策で冬も使える。
ということを覚えておきましょう。
 ハクブン
ハクブン冬に止まっちゃうのは困るけど、ちょっと工夫すれば大丈夫そうね!
 シナモン
シナモン冬季の低温下では保温対策が効果的です。機種によってはヒーター内蔵型も選べます。
コンポストの7つのメリット!

コンポストのメリットも紹介していきます。
- 生ごみの削減でごみ袋代の節約に
- 自宅で簡単に堆肥が作れる
- 環境に優しいサステナブルな生活が実現
- におい対策にもつながる
- 家庭菜園の土壌改良に使える
- 子どもの環境教育にも役立つ
- 災害時の備えとしても活躍
 ハクブン
ハクブンデメリットを踏まえたうえでメリットも理解しておくと、冷静に行動できて失敗を減らすことができるわ。
生ごみの削減でごみ袋代の節約に
コンポストを使うことで、生ごみを家庭内で処理できるようになります。
これにより、可燃ごみとして出す量が減るので、ごみ袋の消費も少なくて済みます。
特に自治体によっては有料ごみ袋を使用している場合、長期的に見るとかなりの節約になるのがポイントです。
普段からごみの量が多くて困っているというご家庭には、手軽に始められて費用対効果も高い方法としておすすめです。
 ハクブン
ハクブンゴミが減って袋の買い足しも減ったし、ちょっぴり家計にやさしいの♪
自宅で簡単に堆肥が作れる
コンポストは、生ごみを分解して堆肥に変える仕組みです。
使い方はとても簡単で、毎日の生ごみを専用容器に入れて混ぜるだけ。
時間をかけて発酵・分解させることで、栄養豊かな堆肥ができます。
これを家庭菜園や観葉植物に使えば、わざわざ土や肥料を買う手間も省けてエコですし、自分の手で土を育てる感覚も味わえるのが魅力です。
 ハクブン
ハクブン毎日ちょこちょこ混ぜるだけで、肥料になるのってうれしい~!
環境に優しいサステナブルな生活が実現
コンポストは、ごみをそのまま捨てるのではなく再資源化する点で、非常に環境負荷が少ない生活スタイルにつながります。
地球温暖化やごみ問題が注目される中、自分でできる小さなエコアクションとして、コンポストは多くの人に受け入れられつつあります。
特別な知識や道具がなくても始められるので、誰でも気軽にサステナブルな暮らしを実践できるのが良いところです。
 ハクブン
ハクブンちょっとした習慣だけど、地球にやさしいって気持ちいいよね♪
におい対策にもつながる
コンポストの中には密閉式のものも多く、生ごみのにおいが広がりにくい設計になっています。
特に夏場など、においが気になる季節には、屋外用コンポストや電動タイプなどを活用することで、不快な臭いをかなり抑えることができます。
また、定期的に混ぜたり乾燥素材を加えることで、発酵臭の抑制にもつながります。
キッチン周りの清潔さを保ちたい方にもぴったりのアイテムです。
 ハクブン
ハクブンにおいが心配だったけど、思ったより全然気にならなかったよ!
家庭菜園の土壌改良に使える
コンポストでできた堆肥は、家庭菜園やガーデニングでの土壌改良にぴったりです。
栄養が豊富なだけでなく、土の水はけや通気性を改善する効果もあり、植物の根が健やかに育つ環境を整えることができます。
家庭で育てている野菜や花の成長が良くなると、育てる楽しみもアップしますし、農薬を控えたナチュラルな栽培にもつながります。
 ハクブン
ハクブンコンポストの土で育てたトマト、甘くて感動しちゃった~♪
子どもの環境教育にも役立つ
コンポストは、ただのエコアイテムとしてだけでなく、子どもの自然教育や自由研究の題材としても最適です。
毎日の食べ残しが時間をかけて土に戻っていく様子を目で見て、手で触れて学べるので、リサイクルや自然の循環についての理解が深まります。
また、親子で協力して取り組むことで、日常生活の中で自然とのつながりを感じる良い機会になります。
 ハクブン
ハクブン子どもが「生ごみってすごいね!」って言ってくれて感動~!
災害時の備えとしても活躍
災害時などでライフラインが止まると、ごみ収集が滞ることがあります。
そんなときにもコンポストがあれば、生ごみを自分で処理できるため、ごみの臭いや害虫発生を抑えられて衛生面でも安心です。
また、バケツ型や密閉型のコンポストは省スペースで置けるため、非常用備蓄の一環として準備しておくのもおすすめです。
日常生活だけでなく、非常時にも役立つ点は大きなメリットです。
 ハクブン
ハクブン停電中も生ごみをそのまま処理できて助かっちゃった♪
ここまで、デメリットとメリットの紹介をしてきました。
 シナモン
シナモン人によってはデメリットをメリットだと思う方もおられると思います。
あなたの感じたままのデメリットとメリットとして参考にしていただければ幸いです(^^
以下からは、おすすめする人とおすすめしない人を紹介していきます。
コンポストをおすすめする人・おすすめしない人の特徴5選
コンポストについて、おすすめする人とおすすめしない人の特徴を5つずつ紹介します。
| おすすめする人の特徴 | おすすめしない人の特徴 |
|---|---|
| 生ごみの量を減らしたいと考えている人 | 毎日の手入れや管理が面倒に感じる人 |
| 家庭菜園やガーデニングを楽しんでいる人 | マンションなどで屋外スペースが確保できない人 |
| エコや環境問題に関心がある人 | ニオイや虫に敏感で神経質な人 |
| 時間に余裕があり日常的な管理が可能な人 | 忙しくてコンポストに手が回らない人 |
| 土づくりや堆肥づくりに興味がある人 | 土いじりや自然素材に抵抗がある人 |
コンポストは、生ごみを減らして堆肥を作ることで、環境への負荷を減らせる便利なツールです。
特に、家庭菜園をしている人や、エコ意識の高い人にはぴったりです。
一方で、毎日のお手入れが必要なため、忙しい人や、ニオイや虫が気になる人にはあまり向いていません。
設置場所もある程度必要なので、住環境によっては不便を感じることもあります。
自分のライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。
 シナモン
シナモンその他、コンポストには悪臭や虫の発生を防ぐために通気性や生ごみの分別管理が必要という注意点があります。
以上のことを踏まえて購入を検討しましょう!
コンポストの初心者におすすめの使い方や注意点を紹介!
そういう方は、まずは以下のことから始めてください。
- 毎日のごみを「資源」に変える流れ
- 準備から始め方までをやさしく解説
- トラブルを防ぐためのコツと工夫
- 慣れたらこんな使い方も!
- 知っておくと安心・お得な知識集
毎日のごみを「資源」に変える流れ
毎日の台所ごみを再利用する仕組みを、やさしく丁寧に紹介します。
作業の基本ステップ(家庭用コンポストの場合)
水分が多いと悪臭や虫の原因に
肉・魚・油物は避けましょう
発酵・分解がスムーズになります
におい・虫の発生がないか確認
野菜・花壇などに活用できます
準備から始め方までをやさしく解説
初めてでも取り組みやすいように、必要な道具と始め方を紹介します。
必要なものリスト(手作りコンポストの場合)
- 容器(バケツやプランターなどでもOK)
- ピートモスやもみ殻くん炭(発酵促進材)
- スコップや混ぜ棒
- ふた(におい防止)
始め方
トラブルを防ぐためのコツと工夫
においや虫を防ぐための保管ポイントを押さえておきましょう。
保管のコツ5つ
- 直射日光を避け、風通しの良い場所に置く
- においが出たら、水分過多かも→乾燥材を加える
- 虫が湧いたら、しばらく投入を控え蓋を密閉
- 定期的にかき混ぜる(週に2〜3回が目安)
- 冬は分解が遅いため、温度管理に注意
慣れたらこんな使い方も!
慣れてきたらコンポストの活用範囲を広げてみましょう。
アレンジ例
- 完熟堆肥を花壇や家庭菜園の肥料に
- 果物の皮や卵の殻でミネラル豊富な土に
- EM菌などを活用して発酵スピードアップ
- コンポスト堆肥+赤玉土でプランター栽培
発酵肥料スプレーの作り方
知っておくと安心・お得な知識集
失敗しないためのコツや、意外と知られていない便利情報を紹介します。
便利な情報
- 一部の自治体では「助成金制度」あり
- コンポスト容器のレンタル制度もある
- 堆肥は家庭菜園仲間にシェアしても◎
注意点
- ペットのふん・油・大量のご飯はNG
- 分解が進まない時は、材料の偏りを見直す
- 夏場は温度とにおい対策を強化すること
 シナモン
シナモンその他、コンポストには温度・湿度管理や投入物の選定など、細やかな注意点があります。
正しい使い方を守らないと、においや虫の原因になってしまいます。
以上のことを踏まえて購入を検討しましょう!
コンポストのデメリット|参考にした商品
記事作成にあたり、参考にした製品を紹介します。
コンポストのデメリットやメリットで共感した方は参考にしてください。
 ハクブン
ハクブン気になった方は、ぜひ試してみてね。
生ごみ減量乾燥機 パリパリキューブライトアルファ(島産業 PCL-33-PGW)
乾燥式でにおいや虫の発生を抑え、初心者でも簡単に始められます。
使い終わったごみはガーデニング用にも◎。
NAXLU 家庭用生ごみ処理機 ハイブリッド式
完全自動で分解・消臭まで行うモデル。
分別なしで生ごみを入れられるので、忙しい家庭にも好相性です。
ダンボールコンポストセット
段ボール箱で作れる初心者向け堆肥化キット。
子どもと一緒に環境学習として楽しめるのも魅力です。
籾殻燻炭 籾殻くん炭
籾殻をいぶして炭化させたもので、土壌改良やコンポストの分解促進・消臭に役立ちます。
軽くて扱いやすく、家庭菜園や堆肥づくりに初心者でも安心して使えますよ。
家庭用 コンポストバッグ
通気性に優れた素材で作られており、生ごみを入れて発酵・分解させることで堆肥が作れます。
折りたたみ可能で場所も取らず、初心者でも気軽に始められますよ。
コンポスト|関連する質問
最後に、コンポストについて、よく検索されている関連する質問と回答を紹介します。
導入や維持の手間、においや虫の懸念、知識不足などが、コンポストが普及しにくい主な理由です。
ウジ虫は有機物の分解を助けることもありますが、不快な場合は発生を防ぐ対策がおすすめです。
コンポストに生ごみを放置するとゴキブリが寄ることがありますが、密閉や管理で予防できます。
毎日混ぜなくても大丈夫ですが、週に1〜2回混ぜると分解が進みやすくなります。
生ごみが露出していたり、水分が多すぎたりすると、コバエが発生しやすくなります。